胃は体のエネルギーの入り口
東洋医学では、胃は「食べ物を受け入れる臓腑」とされ、食事から得られる栄養を取り込む入り口の役割を担います。
脾と連携して消化・吸収を助けることで、全身のエネルギーの源をつくり出していると考えられています。
そのため、胃をいたわることは毎日の元気につながる大切なポイントです。
脾と胃は表裏の関係
五臓六腑では、臓(五臓)と腑(六腑)がペアを組んで働いているとされます。
脾と表裏関係にあるのが「胃」。
- 脾 … 食べ物を「消化・吸収」してエネルギー化
- 胃 … 食べ物を「受け入れ」、次のステップに渡す
つまり、胃がしっかり働いてこそ、脾も力を発揮できます。
五行説における胃の位置づけ
五行説では胃は「土」に属し、消化や栄養のめぐりと深く関わるとされています。
土は「万物を育む基盤」であり、胃と脾が元気であることは、心身の安定に直結する基礎のような存在といえます。
また、季節では「長夏(梅雨〜夏の終わり)」との関わりが深いとされ、この時期は胃に負担がかかりやすいと考えられています。
胃をいたわる生活習慣5選
- よく噛んで食べる
消化の第一歩は口から。ゆっくり食べることで胃の負担を軽減できます。 - 冷たいものを摂りすぎない
冷たい飲み物やアイスなどは胃の働きを停滞させやすいといわれています。 - 食べすぎを控える
胃に負担をかけすぎると、だるさや胃もたれの原因に。腹八分目を意識しましょう。 - 温かい食事・飲み物を中心に
温かいスープやお茶などは胃をやさしく支える味方になります。 - 規則正しい食事時間を意識する
決まった時間に食べることで、胃のリズムを整えやすくなります。
胃の疲れチェックリスト
- 食欲がわかない日が多い
- 食後に強い眠気がある
- 冷たい飲み物でお腹が重くなる
- 胃もたれしやすい
- 体がだるく、元気が出にくい
※複数当てはまる場合は、胃が少しお疲れかもしれません。生活習慣を見直すヒントにしてみましょう。
胃を整えるセルフケア(ツボ編)
- 中脘(ちゅうかん) …みぞおちとおへその真ん中あたり。胃の働きを助ける代表的なツボ。
- 足三里(あしさんり) … 膝の下、すねの外側にあるツボ。昔から胃腸を元気にするツボとして知られています。
お風呂上がりやリラックスした時間に、軽く押してみるのもおすすめです。
まとめ
胃は、体のエネルギーを生み出す入り口。
脾との表裏関係を意識し、食べ方や生活習慣を工夫することで、毎日の元気を支えることにつながります。
健康管理や症状への対応は医師の判断が必要です。ここで紹介した内容はあくまでセルフケアのヒントとしてご活用ください。
お店のご案内
当院では、体質や季節に合わせた東洋医学の知恵を活かした施術をご提供しています。
「最近胃が重い」「食欲が出ない」などのお悩みもお気軽にご相談ください。
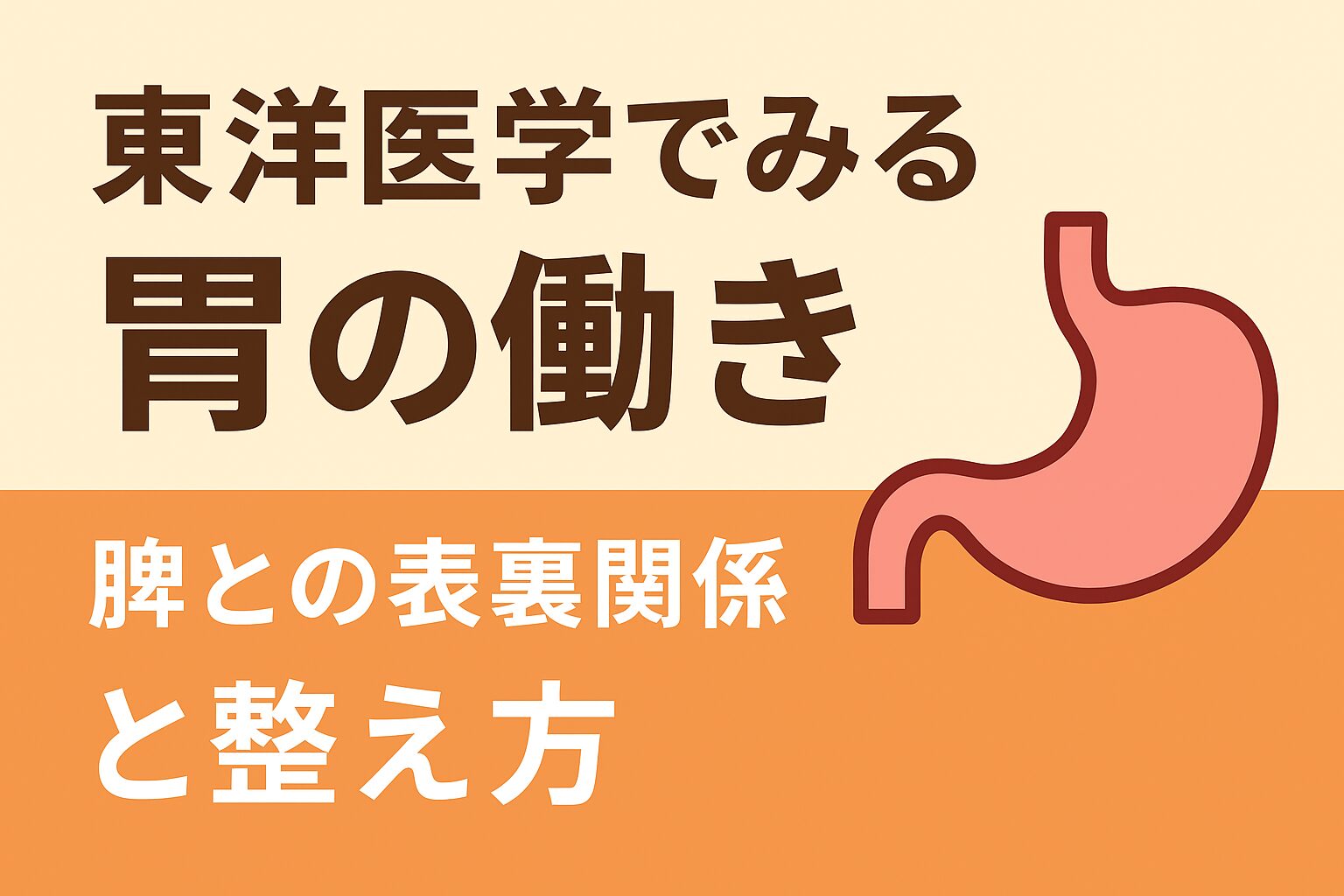

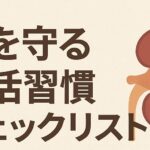
コメント