「脾」という言葉を聞いたことはありますか?
東洋医学では「五臓六腑」の一つとして大切な役割を持ち、食べたものをエネルギーに変えて全身へ届けると考えられています。
ここでは、脾の働きや弱ったときのサイン、日常でできるセルフケアについて分かりやすくまとめました。
脾とは?(東洋医学の基本)
- 食べ物や飲み物を消化・吸収する
- 栄養をエネルギー(気)や血に変える
- 全身に気血を届ける
五行説では「土(つち)」の性質を持ち、体全体のバランスを整える存在とされています。
脾が弱ったときに出やすいサイン
東洋医学的な見方では、脾がうまく働かないと次のようなサインが表れることがあります。
- 食欲が出にくい、食後に強い眠気がある
- 朝起きても疲れが残っている
- 下痢や軟便が多い
- 舌に歯型がついている
- 甘いもの・冷たい飲み物が欲しくなる
- むくみやすい
※これらはあくまで伝統的な見方であり、病気を診断するものではありません。体調に不安がある場合は、専門機関への相談が安心です。
脾を守る生活習慣7選
日常のちょっとした工夫が、脾をいたわるセルフケアになります。
- 冷たい食べ物や飲み物を控える
常温や温かいものを選びましょう。 - 腹八分目を心がける
消化の負担を減らすことがポイントです。 - 規則正しい睡眠リズム
睡眠不足は消化力を弱めやすいとされます。 - 軽い運動を続ける
散歩やストレッチで気血の巡りをサポート。 - 甘いものは控えめに
少量なら補う作用、過剰なら負担になるとされます。 - よく噛んで食べる
消化を助け、脾の働きを軽くします。 - 心配ごとを溜め込まない
東洋医学では「思いすぎ」が脾を弱めるとされます。
脾を元気にする食べ物
「黄色い食材」や「自然な甘味を持つ食材」が脾を補うと考えられています。
- 穀類:米、もち米
- 芋類:さつまいも、山芋
- 豆類:小豆、ひよこ豆
- 野菜:かぼちゃ、人参
- 果物:栗、なつめ
日常に取り入れやすい食材ばかりなので、献立に加えてみると良いですね。
セルフケアに役立つツボ
軽く押したり温めたりすることで、リラックス習慣として取り入れられます。
- 足三里(あしさんり):胃腸をサポートする代表的なツボ
- 三陰交(さんいんこう):血流や冷え対策に
- 陰陵泉(いんりょうせん):水分バランスを整える
まとめ:脾は体のエネルギー工場
東洋医学での脾は、食べ物からエネルギーを生み出し全身へ届ける「工場」のような存在です。
- 冷たいものを控える
- 腹八分目を意識する
- よく噛んで食べる
といった小さな工夫で、体を内側から支えることにつながります。
毎日の食事や生活習慣を見直して、脾をやさしく整えていきましょう。
東洋医学をもっと身近に
「脾」のお話は東洋医学のほんの一部。
実際に生活に合わせたケアや、体質にあったアプローチを取り入れることで、もっと体がラクになる方も多いんです。
当院 「鍼灸マッサージ処 いずみ屋」(習志野市・京成大久保) では、
- 鍼灸・マッサージ
- 保険適用の訪問施術
- 自律神経や慢性的な疲れに特化したケア
などを通じて、皆さまの健康をサポートしています。
👉 「ちょっと体調を整えたい」「鍼灸を試してみたい」という方は、気軽にご相談ください。
地域の皆さまが 元気に毎日を過ごせるお手伝い をしています😊
📞 ご予約・お問い合わせはお気軽にどうぞ!
ホームページページはこちらから→鍼灸マッサージ処いずみ屋
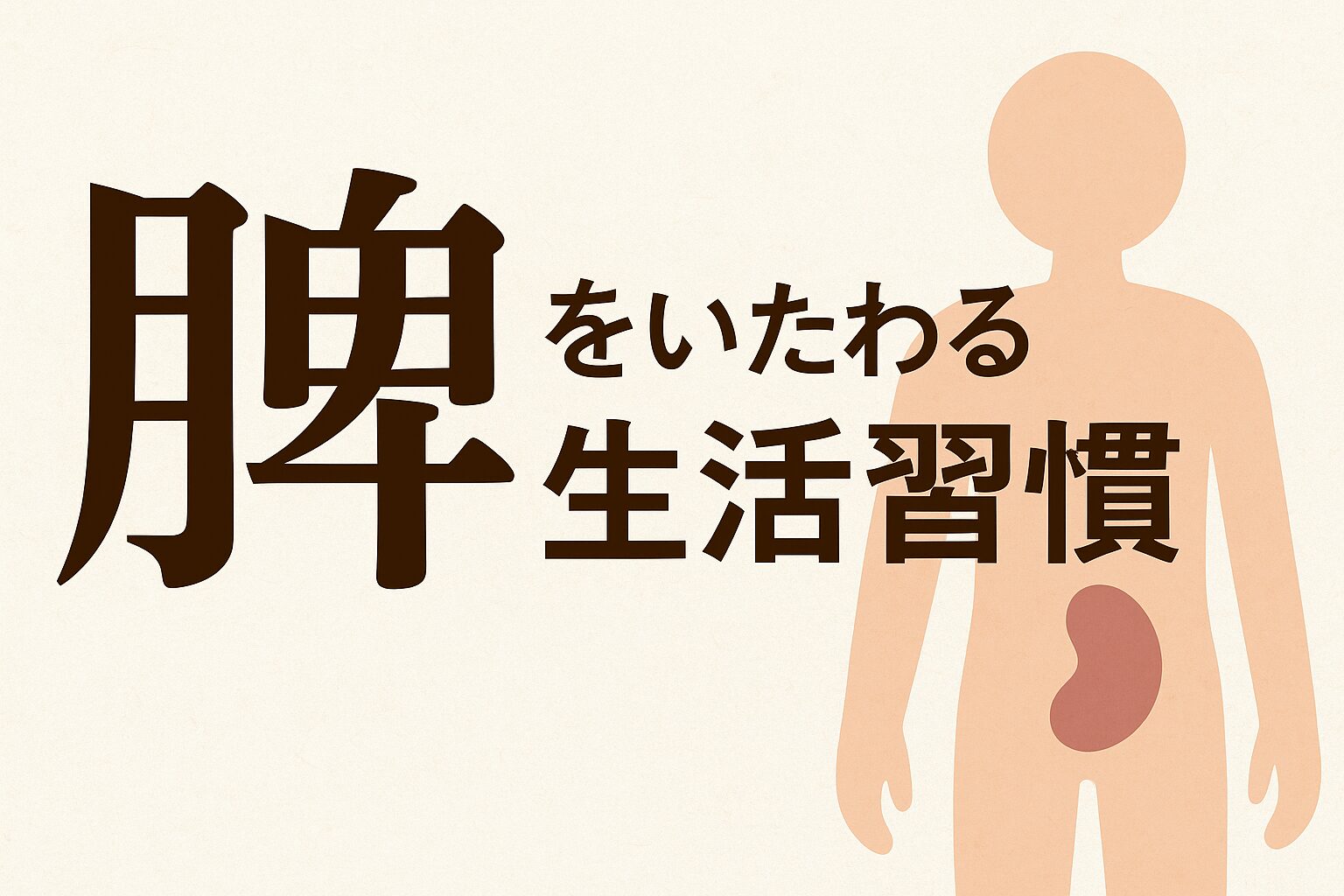

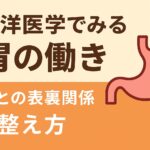
コメント