~鍼灸師が実践している「整える」習慣と東洋医学の考え方
■ 興奮とリラックスのバランス
最近よく耳にする『自律神経の乱れ』。
なんとなく聞いたことがあっても、実はよくわからない…という方も多いのではないでしょうか?
ざっくり言うと、自律神経とは、「興奮」と「リラックス」のスイッチを切り替える体の仕組みのことです。
気候の変化、ストレス、過労などによってこのバランスが崩れると、「自律神経が乱れている状態」と言われます。
■ 自律神経のしくみ
|交感神経と副交感神経|
| 交感神経(興奮モード) | 副交感神経(リラックスモード) |
|---|---|
| 血圧が上がる | 血圧が下がる |
| 腸の動きが弱まる | 腸の動きが活発になる |
| 呼吸が浅く速くなる | 呼吸がゆっくり深くなる |
こうした切り替えを自然におこなってくれているのが自律神経。
でも、現代人はこのスイッチがうまく切り替わらず、不調を感じる方も多いようです。
■ 鍼灸師の私がやっている「自律神経を整える習慣」
私自身も仕事柄、自律神経の乱れには気をつけています。
日常のなかで意識していることは、たとえば次のような習慣です:
- 気づいたときに深呼吸する
- 趣味に没頭する時間を持つ
- 軽い運動(散歩・ストレッチ)
- 自分に合った睡眠時間を確保する
特に子育て中はなかなか思うように時間が取れないこともありますが、
私が実感している大切なことは…
まず奥さんの自律神経を整えること!
パートナーが穏やかでいられることが、家庭全体の健康にもつながります。
そのためには、家事・育児を積極的に分担して「お互いに自分の時間を持てるようにする」。
これこそが、家庭でのセルフケアの第一歩かもしれません。
■ 東洋医学から見る自律神経の乱れ
東洋医学では、「自律神経の乱れ」は主に“気の巡り”の滞りと考えます。
また、精神的ストレスや不安などは以下のような内臓との関係があるとも言われます:
- 怒り → 「肝」
- 不安 → 「心」
- ストレス → 「脾・胃」へ影響
「イライラしたり、不安で食欲がなくなる」などの状態は、東洋医学の観点からも説明がつく部分があります。
■ おわりに
「なんとなく不調…」と感じることがあったら、
まずは「食・睡眠・運動」といった生活習慣を見直すことが第一歩かもしれません。
また、自分に合ったリズムで、無理のないセルフケアをしていくことが大切です。
東洋医学の視点も少し取り入れながら、自分らしい整え方を探してみてくださいね。
※本記事は、筆者の経験や調査に基づいて健康維持・セルフケアのヒントを共有する目的で作成しています。
医療行為や診断を目的としたものではありません。体調に不安がある場合は、医師や専門機関へご相談ください。

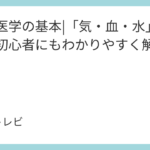

コメント