〜感情・睡眠・血流をつかさどる大切な臓腑〜
こんにちは、しんきゅうパパです😊
今回は、五臓の中でもとくに重要とされる 「心(しん)」 について解説します。
東洋医学では「心は君主の官」ともいわれ、体と心をまとめるリーダー的存在なんです。
心ってどんな役割?
西洋医学でいう「心臓」は血液を全身に送るポンプですが、
東洋医学でいう「心」はそれだけでなく、精神活動や感情の安定にも深く関係していると考えられています。
東洋医学での心の主な働きは次の3つです。
① 血をめぐらせる「血脈(けつみゃく)」の役割
心は、全身に血を送り届ける司令塔。
血の巡りが良いと、顔色が明るくなり、手足の冷えも和らぎやすいとされます。
逆に、心の働きが弱ると…
- 顔色が悪い
- 冷えを感じやすい
- 疲れやすい
など、血流にまつわる不調が現れやすいと考えられています。
② 精神活動をつかさどる「神志(しんし)」
東洋医学では、心は精神や意識、感情をつかさどるとされています。
驚きや不安、緊張、集中力の低下なども、心のバランスと関係していると考えられます。
例えばこんなサインは、心の働きが乱れているときによく見られるとされます👇
- イライラや落ち込みが続く
- 集中力が続かない
- 感情の起伏が激しい
- 不安で眠れない
③ 睡眠と深い関わりがある
東洋医学では、**「心は眠りの質を左右する」**と考えます。
夜になると、日中に活動していた「神(しん)」が心に戻ることで、深い眠りにつけるとされます。
心が疲れていると…
- 寝つきが悪い
- 夜中に何度も目が覚める
- 夢をよく見る
- 朝スッキリ起きられない
こうした睡眠の不調につながることもあります。
心をいたわる生活習慣 5選
ここからは、東洋医学の考え方をベースにした **「心を元気に保つためのヒント」**をご紹介します。
※これはあくまで養生法であり、治療を目的とするものではありません。
1. 睡眠のリズムを大切にする
- 夜更かしは避け、日付が変わる前に寝る
- 就寝前はスマホやテレビを控えてリラックス
- 日中は適度に体を動かして深い睡眠をサポート
2. 赤い食材を取り入れる
東洋医学では「心は赤を好む」といわれます。
- トマト
- スイカ
- 赤パプリカ
- いちご
など、赤い色の食材は心をサポートすると考えられています。
3. カフェインやアルコールは控えめに
コーヒーやお酒は一時的に気分を上げますが、
取りすぎると心に負担をかけ、睡眠にも影響するとされます。
4. 深呼吸でリラックス
緊張や不安を感じたときは、深呼吸で気持ちを落ち着けるのがおすすめ。
「息を長く吐く」ことを意識すると、副交感神経が優位になり、心が安らぎます。
5. ストレスをためこまない工夫をする
- 予定を詰め込みすぎない
- 趣味や好きなことをする時間を作る
- 家族や友人と会話する
こうした「心を休める時間」が、心のバランスを保つカギです。
まとめ
- 心は「血流・感情・睡眠」をつかさどる重要な存在
- 睡眠・食事・ストレスケアが心の養生ポイント
- 日々の生活習慣を整えることが、心をいたわる第一歩
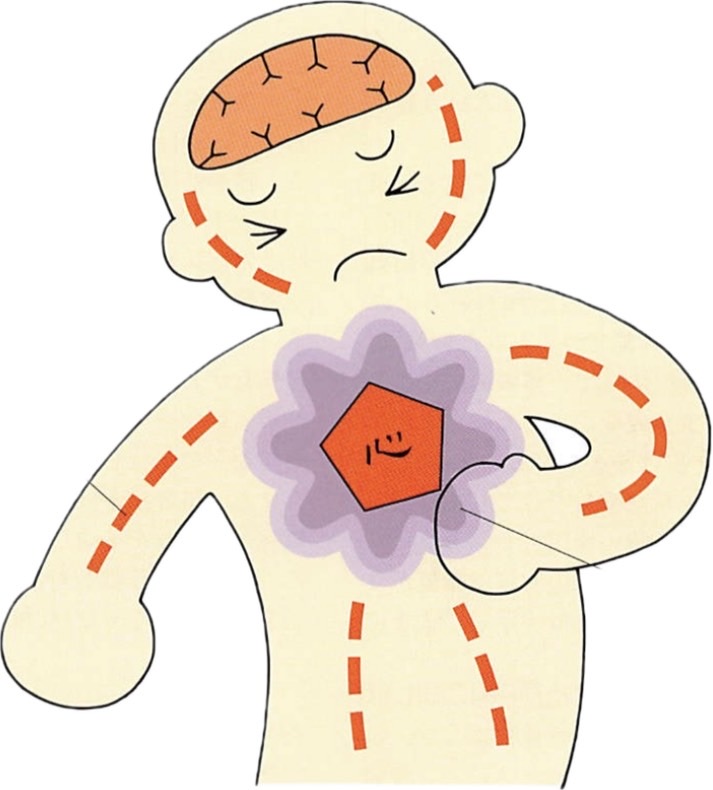


コメント