〜ストレス・睡眠・決断力にも関わる大切な臓腑〜
こんにちは、しんきゅうパパです😊
前回は「肝(かん)」についてお話ししましたが、今回はその 表裏関係(ペア) にある「胆(たん)」について解説します。
東洋医学では「肝胆同源(かんたんどうげん)」ともいわれ、肝と胆はお互いに深い関わりを持っています。
胆ってどんな役割?
西洋医学でいう「胆」は胆嚢(たんのう)を指し、胆汁を貯めて消化を助ける働きをします。
一方、東洋医学では「胆」をもう少し広くとらえ、体と心のバランスに大きく関わる存在と考えます。
東洋医学での胆の主な働きは次の3つです。
① 決断力をサポートする
胆は **「決断をつかさどる」**といわれています。
「何かを決められない」「自信がない」「優柔不断になっている」
そんなときは、胆のエネルギーが弱っている可能性があると考えられます。
② 睡眠の質に関わる
東洋医学の体内時計「子午流注(しごるちゅう)」によると、
夜23時〜1時は胆の働きが活発になる時間です。
この時間にしっかり眠れていると、胆の働きが整いやすいとされます。
- 眠りが浅い
- 夜中に何度も目が覚める
- 翌朝スッキリしない
こんなときは、胆の働きを意識して生活を見直すのも一つの方法です。
③ 肝と連動してストレスをケア
胆は「肝」とペアで働きます。
肝がストレスで緊張すると、胆にも影響が出やすいと考えられます。
例えば…
- イライラしやすい
- 頭に熱がこもる
- 決断力が落ちる
- 寝つきが悪い
こういった不調は、肝胆バランスの乱れと関係している場合があるとされています。
胆をいたわる生活習慣 5選
ここからは、東洋医学の考え方をベースに「胆を整えるヒント」をご紹介します。
※これはあくまで東洋医学の養生法であり、治療を目的とするものではありません。
1. 睡眠リズムを整える
- 夜23時〜1時は「胆のゴールデンタイム」
- この時間にしっかり眠れるよう、早めに寝る習慣を意識しましょう。
2. 緑色の食材を取り入れる
東洋医学では「胆は青(緑)を好む」といわれます。
- ピーマン
- 小松菜
- ブロッコリー
- ニラ
などをバランスよく食べると、胆の働きをサポートすると考えられています。
3. 決断に迷ったら小さな選択から
胆は「決断力」をつかさどるので、迷うことが続くと胆の働きが乱れやすいです。
小さなことでもいいので「今日はどの服を着るか自分で決める」など、
日常の中で決断する習慣をつけるのもおすすめです。
4. 深呼吸でストレスを和らげる
肝胆はストレスの影響を受けやすいペア。
深呼吸や軽いストレッチでリラックスすると、胆の働きも整いやすくなります。
5. 油っぽい食事は控えめに
胆は胆汁を貯めて脂肪を分解する働きがあるため、油っぽい食事が続くと負担がかかるとされます。
揚げ物やこってり料理はほどほどに、バランスの取れた食事を意識しましょう。
まとめ
- 胆は「決断力・睡眠・ストレス」と関わりが深い
- 肝とペアで働き、バランスを整えることが大切
- 睡眠・食事・ストレスケアが胆の養生ポイント


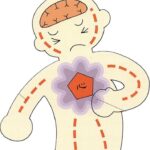
コメント